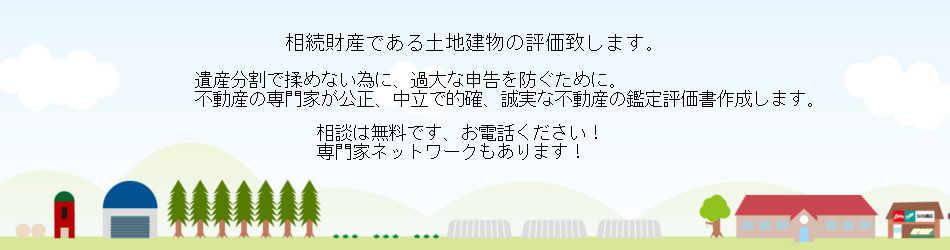評価対象物件に第三者の抵当権などが付いているか、の調査は鑑定評価に含まれるのでしょうか?という質問に答えます。
不動産の価値(経済価値)は、その物件が持つ物理的な側面(広さ、形状、建物の状態など)だけでなく、法的な側面(どのような権利が付着しているか)によっても大きく左右されます。
例えば、利用を制限するような権利(他人のための地上権や地役権など)や、所有権の行使を制約する権利(抵当権など)が存在する場合、それは不動産の価値を減少させる要因となります。したがって、適正な鑑定評価額を求めるためには、権利関係の調査が不可欠です。
不動産鑑定士は、主に以下の方法で権利関係を調査・確認します。
- 登記事項証明書(登記簿)の確認
法務局で取得した最新の登記事項証明書の内容を精査します。- 甲区(所有権に関する事項): 現在の所有者は誰か、過去に差押え等の履歴がないかなどを確認します。
- 乙区(所有権以外の権利に関する事項): 抵当権、地上権、賃借権などが登記されているかをここで確認します。金融機関からの借入による抵当権設定は、よく見られる事例です。
- 現地調査・ヒアリング
登記簿には記載されない権利(例:占有者の存在、未登記の賃貸借契約など)の有無を、現地での観察や、依頼者・所有者へのヒアリングを通じて確認します。
これは、司法書士や弁護士が行うような「権利の有効性を法的に保証」したり、「隠れた権利関係の瑕疵(かし)まで完全に調査」したりする業務とは異なります。原則として登記簿の記載内容を真実なものとして受け入れ、その前提で評価を行うためのものです。
ご依頼の目的によって、権利関係の取り扱いが変わってきますので、鑑定士にご依頼される際には、どのような目的で評価が必要なのかを詳しくお伝えいただくことが、より精度の高い鑑定評価につながります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。