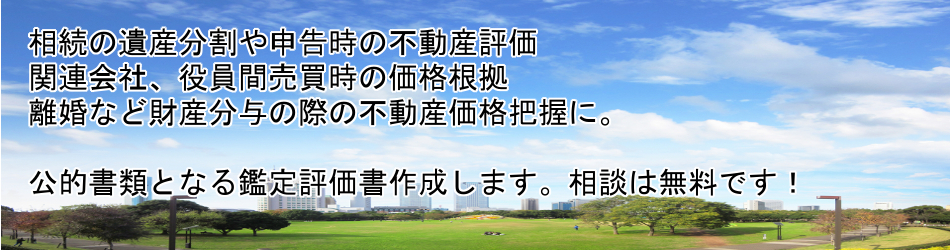元商店だった親の家の相続、まず何をすべき?税金と遺産分割の落とし穴
「離れに住んでいる親の家、昔は商売をしていたけれど、もし相続になったら何から手をつければいいのか?」という相談がありました。
ご実家の相続を前に、漠然とした不安を感じている方は少なくありません。特に、ご実家が元店舗や事務所だった場合、手続きがより複雑に感じられることでしょう。
相続の2大課題。「税金」と「遺産分割」は全くの別問題
相続が始まると、大きく分けて2つの課題に直面します。
-
税金の課題:国に相続税を納める
-
分割の課題:相続人同士で遺産を公平に分ける
この2つは目的が全く異なるため、不動産の価値の考え方も違います。ここを混同してしまうと、後で「こんなはずでは…」という事態になりかねません。
課題① 税金の話は「税理士」へ相談が大原則
まず、相続税がいくらになるか、いつまでに納めるか、といった「税金」に関する一切は、税務の専門家である税理士に相談するのが大原則です。
税理士は、相続税を計算するために「相続税路線価」という国が定めた基準で不動産を評価します。これはあくまで「税金を計算するための特別な価格」であり、注意したいのは、この価格が「実際に不動産が売れる価格」ではないということです。
課題② 最も揉めやすい「遺産分割」と不動産鑑定士の役割
相続税の納税以上に、ご親族間でトラブルに発展しやすいのが、財産の分け方を決める「遺産分割」です。
なぜ揉めるのか?その最大の原因は、不動産のような分けにくい財産の価値がいくらなのか、共通の認識がないからです。
ここで、よくある失敗例をご紹介します。
【失敗例:相続税評価額で遺産分割してしまったケース】
ご兄弟3人で、元商店だったご実家を相続したとします。長男が家を継ぎ、他の兄弟2人には現金を渡す「代償分割」を行うことになりました。
税理士に計算してもらった相続税評価額(路線価ベース)は「2,400万円」でした。
そこで長男は、2,400万円を3人で割った一人分800万円を、兄弟2人にそれぞれ支払いました。これで公平に分割できた、と誰もが思っていました。
しかし数年後、次男がふと近所の不動産屋でご実家周辺の相場を聞いたところ、実際の市場価値(時価)は3,000万円に近いことが判明します。
次男はこう思うでしょう。
「本当は一人1,000万円もらえるはずだったのに、800万円しかもらえなかった。兄さんだけ200万円も得をしたじゃないか…」
この不公平感と不信感が、その後の親族関係に深い亀裂を入れてしまうのです。
【正しい解決策:客観的なモノサシを用意する】
このような悲劇を防ぐために、不動産鑑定士がお役に立ちます。
私たちは、税金計算用の価格ではなく、「今、この不動産を第三者に売ったらいくらになるか」という客観的で公平な時価を割り出し、『不動産鑑定評価書』という公的な書類で証明します。
この鑑定評価書があれば、「この家の時価は、専門家が評価した結果、3,000万円です」という、相続人全員が納得できる、議論の余地のない共通のモノサシが手に入ります。
このモノサシを基にすれば、「家を継ぐ長男は、他の兄弟2人に1,000万円ずつ支払う」といった、誰もが納得できる公平な話し合いが可能となり、円満な遺産分割をスムーズに進めることができるのです。
まとめ:相続が始まったら、まずやるべきこと
ご実家の相続、特に元商店など少し複雑な不動産の場合は、以下の2つの準備を並行して進めることを強くお勧めします。
-
税理士に相談する
まずは相続に強い税理士に相談し、相続税がいくらになるか、納税資金はどうするか、といった税務面の全体像を把握しましょう。 -
不動産鑑定士に相談する
同時に、ご兄弟など他の相続人との間で不動産の価値で揉めないよう、不動産鑑定士に依頼し、公平な話し合いの土台となる「客観的な時価」を把握しましょう。