登記事項証明書を調べていたら地役権が設定されている土地を見つけました。
地役権とは他人の土地を利用することができる権利で、登記事項証明書には乙区に記載されます。
一般的には通行するために設定することが多いと思いますが、
今回の地役権の内容は記載されている特約によると
所有者は工作物を設置することができないこと等が書かれてました。
こういう土地を購入する場合は利用に影響がありますので当事者と話し、削除できるかなどよく確認しましょう。
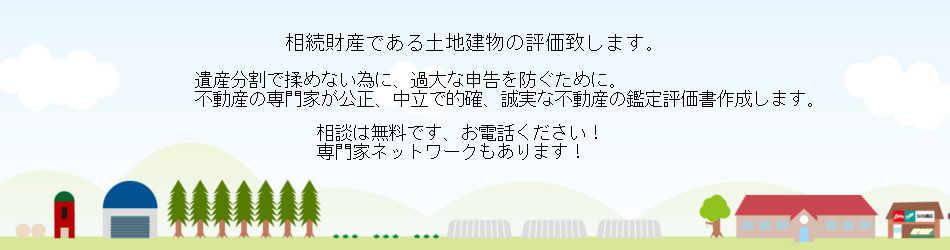
登記事項証明書を調べていたら地役権が設定されている土地を見つけました。
地役権とは他人の土地を利用することができる権利で、登記事項証明書には乙区に記載されます。
一般的には通行するために設定することが多いと思いますが、
今回の地役権の内容は記載されている特約によると
所有者は工作物を設置することができないこと等が書かれてました。
こういう土地を購入する場合は利用に影響がありますので当事者と話し、削除できるかなどよく確認しましょう。
最近は個人の方も不動産投資しているとききました。
売り物件もよく出ているのか土地勘のない土地でも転売のため購入している、とか。
なかには安いから、という理由だけで間口2m以下の建築不可のような土地でも購入している人もいるという。
そういうの転売できるんでしょうか?できたら購入前にでも一度見せてほしいですね。なにかアドバイスできるかも。
ある時建物のみを鑑定してほしい、という相談がありました。
通常、建物は土地の立地環境があっての建物ですから、土地と建物全部を評価しその内訳として建物の価格を算出します。
ですので実際は通常の土地と建物を評価する形と何ら変わらずなんですがなにせ「建物だけ」という言い回しから早く、安く、簡単に鑑定できるものと思って相談されることもありますが残念ながらそうではないのです。
今の家賃が安すぎる(高すぎる)から賃料鑑定してほしい、それで交渉するから、という相談を受けることがあります。
鑑定書では適正な賃料を出して提出するのですが、特に弁護士さんに多いのですが交渉するのにつかうから何倍にして、とか半額で、とか鑑定の賃料を指定されるときがあります。
申し訳ないのですがうちは適正な価格、賃料の鑑定書しか出しません。
まあ何倍の賃料を書かせておけば交渉に有利なのはわかりますが鑑定書はそういうものじゃないので。
違法建築の不動産を相続した依頼者からの相談。
結局鑑定はしませんでしたが、売買時、土地を分割したため違法建築状態になった不動産を買ったのを相続したとのこと。
通常仲介業者が入るか、銀行ローンで買っていれば問題点が浮き彫りになったと思いますがこのケースでは個人間売買でなおかつ現金で購入したため違法状態が表に出ず売買が成立したのでしょう。
違法建築状態であるなら建替え時は当然適法状態の建物にする必要があり、またこのまま売買するにしても仲介業者を通さず、現金で買える買い手を見つけることは困難と思います。
鑑定したとしても評価は下がってしまうでしょう。
個人間売買はこういうリスクがあるので注意が必要です。
今回の話は売主がそもそも不動産関係者らしいので全部わかってて売りつけたんじゃないかと勝手に邪推してます。
不動産の情報の格差があったため買主は不利益を受けたので、個人間売買はできれば不動産に詳しい、信頼できる人に購入する不動産をみてもらっては、と思います。
不動産業者さんは仲介に入って仕事したいから話しづらいと思いますので。いなければ私にでも相談してください。
依頼者からの相談。
バブル時代の土地価格を知りたいという相談でしたが当時はもう30年以上前になることからさすがに不動産鑑定評価書を作成するのは困難だと断りました。
ただよくある税務署提出のため不動産の譲渡所得税計算に必要な取得費を知りたいのではなく、相続した不動産だったので単に当時の土地価格の妥当性を知っておきたいとのこと。
それなら不動産鑑定評価書じゃなく当時の近隣で売買された取引情報を集めて土地の相場を掴むぐらいのことでいいですか?ということで了承いただきました。
今回は依頼された当時の近隣で実際に売買された取引を見ると戸建住宅の土地の坪単価300万~350万位でした。今からは考えられない価格で、バブルを知らない世代からすると疑問に思う取引で当然だったと思います。
今回のような古すぎる時点では不動産鑑定評価書は作成できませんが当時の売買取引情報くらいでいいのならいつでもどうぞ。
依頼者からの相談。
親族同士で隣り合った畑をもっているが一方を売ることにした。
しかし親族同士ということもあり土地の境界が不明であったため、買い手からクレームがきておりどうしたものか、と。
境界が問題になることはよくあります。
基本的には現状の工作物の状態と地図(公図等)をくらべて簡易測量して照らし合わせて、
この辺が境界と目処をつけて話し合ってほしいですが揉めるときはなかなか決まらないことのほうが多くて。
最終的には専門家である土地家屋調査士さんに依頼してみては、と伝えました。
なるべく売る前に測量して境界ははっきりさせておいたほうが良いと後々トラブルにならなくていいんですが。
測量したら土地面積もちゃんとわかりますし。畑なら実際は大きかった、小さかったということもあると思いますし。
税理士さんから固定資産税交換の特例時の鑑定評価を聞かれた件で、固定資産税の交換の特例についておさらいしておきます。
国税庁webより、
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
特例を受けるための適用要件
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
土地は宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他
建物は居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用
(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。
この資産の時価を鑑定評価で算出することになります。
注意事項
(1) この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。
(2) この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。
土地建物と土地を交換した場合には総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、
交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。
また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになりますので、建物についてこの特例は受けられません。
この場合、交換で譲り受ける建物の価額が譲り渡す土地の価額の20%を超えるときは、土地についてもこの特例が受けられませんのでご注意ください。
隣地を売買するとき、鑑定評価では限定価格となることがあります。
不動産鑑定評価基準によると
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
限定価格を求める場合を例示すれば次のとおりである
1.借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
2.隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
3.経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
とあります。
限定価格は特定の当事者間においてのみ経済合理性が認められる価格です。
併合を目的とする売買においても併合による増分価値が発生しない場合においては第三者間取引の場合とその取引価格に差異が見られないので限定価格とはなりません。
また併合により生じる増分価値は併合される両者が寄与して表示させたものであるので、両者に適正に配分すべきです。
よくある隣接不動産の併合の例として、併合したら間口、奥行きがとれて画地が良くなる場合、併合により無道路地が道路に接面することになる場合、狭小地、不整形地が併合される場合などです。
隣接地と併合することにより両者の土地の価値は上がりますから売買のときはまずお隣に声をかけろ、と言われたことがあります。そのほうが買手を探し回るより効率いいですしね。
またお隣同士の売買では不動産の仲介業者を通さない取引もみられますが、併合することによる増分価値を適切に反映させて売買価格をきめるのは難しいと思いますので鑑定価格を参考にした交渉をお勧めします。
鑑定価格をお互いの基準にして、どうしても隣地がほしいので少し高くなるのは仕方ないかとか交渉の目安にしてください。