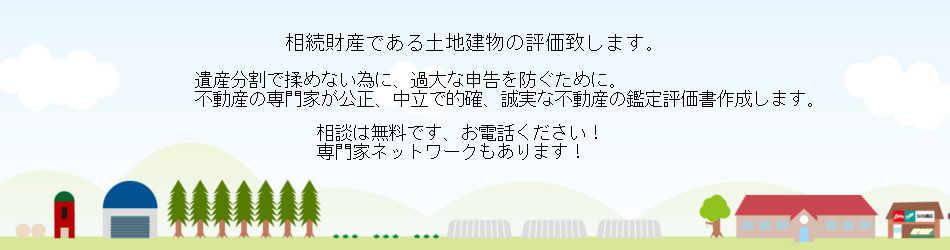現行制度上、相続人以外のものは被相続人の介護を尽くしても、相続財産を取得することはできません。
そこで介護者の不公平感をなくすために新法が設立されました。
新法1050条では被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をして特別の寄与をしたこと、被相続人の親族であること、とあります。
長男の妻が夫の親の療養看護を無料でしたケースなどが想定されます。
その場合、寄与に応じた金銭の支払いを請求することができるとあります。
どうやって請求するのでしょう?
新法1050条2、3項では当事者間の協議が調わない、できない場合は家庭裁判所に処分の請求ができ、家庭裁判所は特別寄与料の額を定める、とされてます。
特別寄与者が被相続人の親族と限定されており要件がややこしいですが少しは相続紛争がおさまればと思います。