東京都心の2月オフィス空室率が5%を超え平均5.24%と三鬼商事が発表したニュースを目にした。
目安の5%を超えるのは5年8ヶ月ぶりだそうで。
では大阪は?
三鬼商事データでは地区別をみるとすでに船場と新大阪は5%超えてました!
船場は2020.11月から5.09→5.22→5.18→5.01%
新大阪は2021.1月から5.06→5.37%
2月の大阪は平均3.74%だけどやっぱり緩い上昇傾向にありますね。
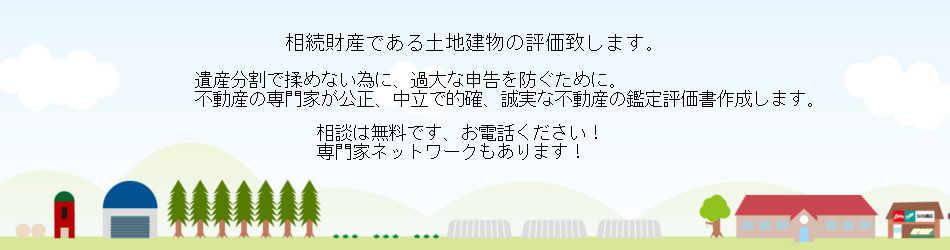
東京都心の2月オフィス空室率が5%を超え平均5.24%と三鬼商事が発表したニュースを目にした。
目安の5%を超えるのは5年8ヶ月ぶりだそうで。
では大阪は?
三鬼商事データでは地区別をみるとすでに船場と新大阪は5%超えてました!
船場は2020.11月から5.09→5.22→5.18→5.01%
新大阪は2021.1月から5.06→5.37%
2月の大阪は平均3.74%だけどやっぱり緩い上昇傾向にありますね。
隣地が空家で購入の相談について。
隣地は何十年も前に相続があり、相続人がまた10人以上いるが遠方に散らばっている状態でしかも亡登記(亡くなってる方の名義)もある。
どうやって交渉するものか、という類です。
どうしたものか、弁護士さんに伺いました。
結論としてはどうしょうもない、と。
まず、各所有者の現在の所在を掴むのが困難。弁護士でも裁判前提でないと住民票は取れない。
次に所在つかめても経験上数十人の全員の承諾を取るのは難しい。
亡登記はもう宙ぶらりん状態になっている。これは家庭裁判所で手続きをするにしても他の相続人が不明、お金もかかるのでやはり困難。
ということで、現時点ではかなり実現可能性の低い取引になるようです。
不動産を売買したけど昔、昭和の時買った不動産なので取得費がわからない。鑑定でなんとか当時の価格だせないのか?
という相談がありました。
取得費は不動産を売った時の譲渡所得に税金がかかりますがその計算方法に必要なのです。
確定申告時期によく聞かれるかんじですね。
国税庁HPより、
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
この課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
とあります。
取得費がわからないときは売った金額の5%相当額を取得費とできる、とありますがそれでは税金が高くなりがちです。
だから鑑定で適正な取得費をだしてほしいというお話ですが、結論としてうちでは出しておりません。
鑑定評価書を作成するに当時の不動産状況、周辺環境など不明点が多く適切な資料も集めることができないので鑑定評価書は作成できないからです。
また意見書でも、と言われますが最終的に価格を提示するとなるとやはり鑑定評価のガイドラインを遵守する必要があるので同様にお断りしております。
じゃあどうすれば?となりますが同様の取得費不明の相談を受けたことがある税理士さんにどうしているのか伺いました。
まずよく聞く市街地価格指数を使って昭和当時の価格を出す方法もあるが、市街地価格指数自体、対象エリアが広くて根拠に弱いと思いその税理士さんは採用していないとのこと。
開発された戸建てを買ったのなら当時のパンプレットやご近所さんに聞く、それ以外なら建ててもらった工務店のパンフレットや担当に聞く、
または登記事項証明書(法務局で取れる謄本です)に載っているローン金額をみる、
など所有者さんは諦めずに地道に根拠仕様を集めてほしいということでした。
容積率がオーバーした物件を購入した人がいた、という話を聞きました。
(注:建物の延床面積が定められた以上の面積になっている状態)
そういう物件は住宅ローンが利用できなかったりして現金を用意するのに大変苦労したらしい。
そうですよね、普通そこまで注意しないですよね。
物件購入前に市役所の都市計画課などにいったら定められている容積率を教えてくれます。
(例:200%なら土地面積の200%までの建物延床面積になります)
さらに、物件が接道する道路幅や用途地域によって決まったりしますのでご注意。
(例:前面道路が4mで住宅系用途なら4m×4/10=160%の容積率になるとかあります)
要は市役所の都市計画課などで実際建てられる容積率を聞き、容積率オーバーしてないかまで教えてもらうこと、ですね。
東京
戸建て需要高まる。
テレワークなど家で仕事するスペースが必要、業者問い合わせ80%増。
利便性の高い郊外を求める人も増加。空き家問い合わせ50%増。
コロナウイルス後は状況が一変している。前は家賃が高くても借りる人は多かったが今は安くしないと借りてくれない。
都心はオフスビルに空きがある。
今まで空かなかったビルが突然空いたり大型店舗がなくなったりする。6ヶ月前申告で退去するのが通常で、4月頃退去決めた人がそろそろ出ているのではないか。
3年前からインバウンド需要でバブルに似てたが今はホテル売る物件もある。
大阪
心斎橋筋商店街、6月は前年比6割まで戻ったが7、8月は感染拡大、ミナミ一部影響があり再び3割まで落ち込む。
市内ホテル、9月の連休前は稼働率約20%、4連休で約50%。GoToトラベルの影響もあって増えたか。
温泉旅館、4連休中は初めて満室になった。ただし団体客利用はなし。
USJ近くのホテル、4連休で満室になる。その後は5割程度。
ミナミのホテル、4連休50%まで戻る。まだ厳しい。インバウンド戻らないと厳しい。
ミナミのホテル、閉めたホテルはたくさんある。インバウンドのお客が一切いない。4連休はずっと満室。
道頓堀のたこ焼き屋、4連休は好調だった。
道頓堀
づぼらや閉店、ドラックストア閉店、飲食店閉店などみられる。
神戸
南京町、例年レベルに戻る。連休後も7-8割まで戻る。
京都
寺町京極商店街、7-8割まで戻ってきた。
清水寺、国内観光客がもともと多く、例年並みの人出がある。
4連休は回復傾向だったがミナミとかインバウンド需要に頼ってたところはまだ厳しい状況が続いてますね。
R2.7.1時点地価調査発表
全国変動率(%)前年との比較
住宅△0.1→△0.7、商業1.7→△0.3、工業1.0→0.2となりました。
大阪府は
住宅0.4→△0.3、と7年ぶりに下落に転じ、
商業8.7→1.8、と上昇幅は小さくなったが8年連続の上昇、
工業1.6→0.3、と同じく上昇幅は小さくなったが5年連続の上昇となりました。
住宅地は後半に新型コロナウイルスの影響による不動産市場の停滞などがあり、
商業地は前半は上昇傾向の地点が主だったが後半に新型コロナウイルスによる景気減退から下落傾向に向かった。
特にインバウンド需要の強かった地点はその反動から強い下落が見られる。
今回の地価調査は後半に新型コロナウイルスの影響がみられており、今後の地価も引き続き新型コロナウイルスの動向に注意すべき。
住宅上昇率上位地点
福島区 4.6→2.7
天王寺区4.8→2.5
北区 3.5→1.6
商業上昇率上位地点
淀川区 22.6→7.2
北区 19.1→5.3
天王寺区10.0→4.3
建築基準法の一部改正がありました。
建築物の適正な維持管理、安全性の確保を中心とする改正です。
いくつか気をつけようと思う点を抜粋すると
安全性の確保では、
空き家など既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設があります。
建物を放置することにより危険、衛生上有害となる恐れがあると認められれば、修繕など維持保全に関する指導、助言ができるようです。ですが、某市役所の話ですと少しは進みますがこれだけではまだまだ空き家問題は難しいそうです。
容積率関係では、
老人、福祉ホーム等の共用廊下又は階段のように供する部分の床面積は容積率算定基礎となる延べ面積に算入しないものになりました。
建ぺい率では、
防火地域内の延焼防止性能を有する建築物、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物等の制限が10%緩和されます。準防火地域が緩和されるのが大きいですね。
令和元年7月1日時点の地価調査が発表されました。全国的に上昇傾向が強くなりましたね。
大阪圏(大阪、兵庫、京都、奈良)は住宅が去年0.1→0.3%の上昇、商業が去年5.4→6.8%の上昇。
商業地の上昇率は東京圏(4.9%)より高いのですね!
大阪8.7%と京都7.1%の変動率が沖縄12%についで高い結果が反映されています。
大阪の商業地で上昇率が高い区は、西区27.7%、浪速区22.9%、淀川区22.6%、北区19.1%、中央区16.2%の上昇。力強い。
下落してる場所でも旭区、東住吉区、大東市だけが去年と同じ数字で△0.4~△0.6%程度。
大阪の住宅地は上昇率が高い区は天王寺区4.8%、福島区4.6%、浪速区4.3%、北区3.5%の上昇。なかでも天王寺区は去年1.4%からの大幅な上昇となってます。
下落してる場所は東部や南部で多く、△0.1~△1.1%程度。まだ中心部から離れると厳しいか。
八尾市の道路後退を調査していたとき。
現場は全面4m未満の道路だったので、建替えするときには道路が4mになるように中心から2mずつ後退することが必要になると考えられます。
八尾市役所でセットバック(後退)の有無を尋ねると、一方後退で4.35m後退する必要があると言われました。
それは道路の向かい側は鉄道が走ってるため、現場側が一方的に後退する必要があるのです。
でも普通4mじゃないかな?と思い尋ねたところ、敷地が300㎡以上で開発行為に該当する場合は4.35mになるんですね。
開発行為に該当すると開発時に必要な敷地面積、床面積、駐車場の確保台数などその他規制もよく調べておく必要があります。
マップナビおおさかを見ていると建築基準法附則第5項(道路法による道路のみで幅員4m未満)という道路があります。
4m未満なのでセットバックを大阪市都市計画局建築指導部建築企画課に確認すると、
この道路は42条2項と同じく道路の中心より2mずつ後退する必要があります。42条2項道路と違うのは、建築申請するときには道路の明示書を添付してください、とのことでした。